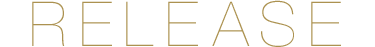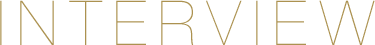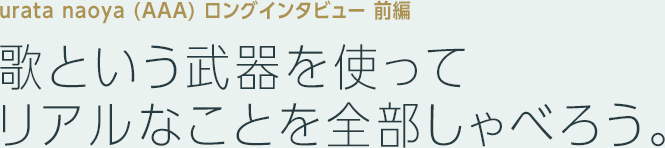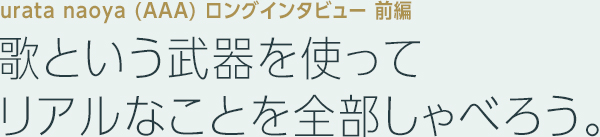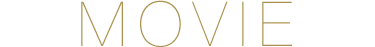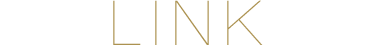2017年4月26日(水)にリリースされるurata naoya (AAA)のオリジナル・アルバム『unlock』。音楽への愛、作り手への敬意をしのばせた静かな筆致で数々のトップ・アーティストを紹介してきた音楽ライター・藤井美保のインタビューで、本作に込められた浦田直也の想いに迫ります。
text by 藤井美保 photo by 小境勝巳
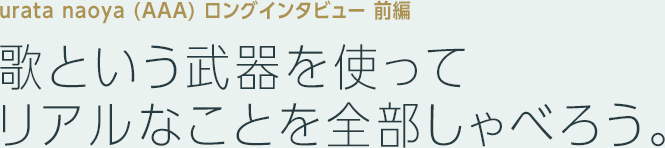
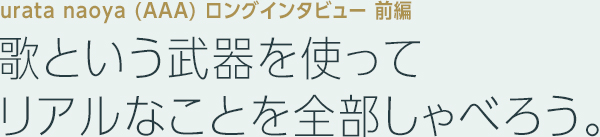
輪郭が濃い。初対面の浦田直也に、その内面がしっかり一筆書きされたような佇まいの強さを感じた。それは、これまで写真の彼から受けていた印象とは違うものだった。どっちが真実とかではない。真実は自分のなかにあればいいと知った者の無防備でオープンさが今の彼にはある。そして、それが他者を爽快にするのだ。久々のオリジナル・アルバム『unlock』。そこに刻まれた自らの解放を訊いた。
---まず、今作に臨むにあたってどんな心境だったのかを聞かせてください。
浦田 実はオリジナル・アルバムは1stの『TURN OVER』以来なんです。2ndはカバー・アルバム、3rdは既発作と他の方とのコラボをまとめたものでした。ということもあって、自分の気持ちを自分で書く作品を作りたいと思いました。ふと思えば、AAAとして11年、歌を歌う人となって12年目の34歳。歳とったとは思わないけど、「若いね」と言われるがむしゃらな20代とも違う。その今だからこそ言える言葉があるなと思ったんです。なんかようやくそう思えました。
---俯瞰で自分を眺められる時期が来たんですね。
浦田 べつに何かを隠したり嘘をつくわけじゃなくても、本当はこう言いたいのに自分を作らなきゃと思ってしまうことってあるじゃないですか。僕だったら、歌手としての自分とか、AAAの浦田直也としての自分とかを考えてしまったりする。たぶんどんな人でも、公共の場で「これは言っちゃいけないかも」と留めてることってありますよね。べつに無理してたというほどのことじゃなくても、そういうことって自分にもあったんだろうなと。それを一度吐き出すことによって、また新しく自分のやりたいことが出てきたり、何かスッキリした気持ちで違う目標を見つけることができるんじゃないかという予感がありました。
---パブリック・イメージとのギャップは、どんなアーティストにとっても常なる悩みですよね。
浦田 でも、「心の内を語ります」となると、過去を否定するだけになってしまうので、それは違うなと。だったら僕は、歌という武器を使って、音楽というフィルターをかけながらリアルなことを全部しゃべろうと思いました。
---そういったハッキリとした動機が、今作の強さにつながってるんですね。34歳というといわゆる働き盛り。男として仕事を残したいという感覚もあったりしますか?
浦田 それはあります。もちろんグループとしてもそうなんですけど、ソロとしてもちゃんと自分の考えたものを一つひとつ残していきたいという感覚に変わってきました。その場その場で楽しければいいとか、歌ってて気持ちよければいいとかじゃなくて。だから今回、こだわりも強かったんじゃないかなと思います。
---ソロへの欲求が、以前とは違うものになっていますか?
浦田 表現したいものが増えたのかもしれないです。人から求められているものと自分が発信したいものってズレてたりするので、自分的にはそのズレの部分も見てほしい。「みんなの期待に応え続けます」だけじゃなくて、時には「やりたいのはコレなんです」と提示する瞬間があってもいいのかなと思うようになりました。
---で、やるからには、作詞は全部自分でと?
浦田 はい。自分の気持ちを話して作詞家さんに書いていただくのがワルいわけじゃないけど、そうやって出来た歌詞はもう自分の言葉じゃなくなってると思うんです。「僕の気持ちを書いてもらった曲です」と言えば、聴いてくれる方たちは「そうなんだ」と思ってくれるかもしれないけど、僕にとってそれは、人の言葉に喩えられた自分でしかない。そうなると、歌うときにはその自分を演じなきゃならなくなるんです。でも、自分で書けば、どんな歌い方をしても自分。格好つけようがつけなかろうが、自分の言葉だからそこにウソはないわけです。
---『unlock』というタイトルは、そういった思いにピッタリですね。で、今回既発作を調べていてシャレ(?)に気づいてしまいました。2ndアルバムが『UNCHANGED』、3rdが『un BEST』。表記はべつにしてみな「UN」がついてる。「アッ、浦田直也の頭文字だ!」と(笑)。
浦田 そうなんです。2ndのときに、小さい頃から口ずさんでいた曲をカバーしたいと思って、そもそもなぜそれをやりたいのかを考えたんです。で、その答えが、「好きなものは変わらない」ということを言いたいから。じゃあそれをタイトルにしようと思い、「変わらない」という英語を検索したら、偶然出てきたのが『UNCHANGED』。「オッ、"UN"だ!」とうれしくなって、それがきっかけで、次からの作品にも全部頭には「UN」をつけようと思いました。
---それでシリーズ化したんですね。『unlock』を思いついたのはどのタイミングでしたか?
浦田 心に留めていたものを外に出そうと漠然と思ってたときに、「解放」とか「解除」という意味の英語を検索したんです。そしたら『unlock』と出て、「これってもう運命じゃん!」と思いました(笑)。
---ワーッ!
浦田 これは解放しろってことなんだなと思って、「よし、思ってることを全部書こう」と思いました。
---あ、逆にそこから?
浦田 はい。その段階では具体的なことまでは見えてなかったけど、とにかくガチガチに固めている自分を全部解放しようと思いました。
---「変わらない」という意味の『UNCHANGED』からシリーズが始まっているのも面白いですね。「変わらない」浦田さんの根底を今回出してるわけですから。
浦田 ホント運命です。
---さて、ここからはサウンドや具体的な作業について訊いていきたいと思います。今回は非常に骨太なロック・サウンドとなってますが、それは最初から意図してたんですか?
浦田 ソロのライブを想像したときに、バンドさんと一緒にステージに立ってる自分の姿が浮かんだので、曲選びのときからそういうオーダーを出してました。コンピューター系ではなく、その時、その時の感情で変わるような音にしたかったんです。

---選曲の基準は?
浦田 直感です。聴いてすぐ「あ、この曲カッコいい」、「この曲に歌詞書きたい」と思ったものを、迷いなく決めていきました。
---方向性がクリアだったんですね。編曲のats-さん、大西克巳さん、清水武仁さん、日比野裕史さん、みなさんギタリストですもんね。
浦田 そうなんです。僕自身ももともとそういう音が好きだったと思うんですよ。仕事じゃなく、カラオケとかでロック系を歌うと、気持ちいいなと思ったりしてたんで。
---具体的な作業については、リード曲の「空」からいきましょう。
浦田 この曲のサビを聴いたとき、今っぽくない耳の残り方がいいなと思いました。ひょっとして40代くらいの方たちが聴いたら、なんか懐かしいと思える感じなのかもなと。メロディに明るさがあるからこそ、それと対局にあることを書いて、聴き終えたときに何かひっかかる曲になるといいなと、そんなところから始まりました。具体的に「空」をテーマにしようと思いついたのは、飛行機でこの曲を聴いてたとき。そういえば、けっこう「空が好き」と言ってるし、インスタにもよく空の写真を上げてるなと思い出して、「空」に自分の気持ちを重ねたら面白いかもと思ったんです。ノートに「晴れ、青い、夕陽、赤い、曇り、雨、爽やか、柔らかい、落ち込む、涙」と書き出してるうちに、全体像がまとまっていきました。なんか、空みたいな人になれたら気がラクなのになと思ったんです。
---空みたいな人?
浦田 雨が降れば、出かける予定の人は困るけど、その一方で「ああ、雨降ってくれてよかった」という人もいる。同じように、僕が歌うことを喜んでくれる人もいれば、「こんな歌、歌ってほしくない」と思う人もいる。でも、それをいちいち気にするんじゃなくて、空の変化のように、ただまんま当たり前に受け入れて、自分はこういう人間なんですって言えればいいなと。つまり、自信を持ちたいということですね。
---たしかに「空」には、そういう内面の決心みたいなものを感じました。普段から言葉をノートに書きとめたりする人ですか?
浦田 友だちに何かを説明するときにしたたとえ話が「あ、今の面白い」と思ったときは、書きとめたりしてます。今回言葉につまったり、なんかハマんないなというときに、そのメモがけっこう役に立ちました。
---全体的に作詞の作業はスムーズでしたか?
浦田 僕は、浮かんだから書くというタイプではなく、書くと決めて書くタイプなんです。だから、スラーッと出て来たときは早い。逆に、出てこないときは一旦やめます。悩んじゃうとどうしても欲が出て、カッコいい自分を見せようとしちゃうので。
---自分のことがよく分析できてますね。
浦田 作詞経験がそれほど多いわけじゃないんですけど、ま、だから、それだけ書きたいことがあったんだと思います。あと、年齢を重ねてきたってこともあるかな。今さら「ダメだよ、そんな言葉」と言う人もいないだろうなと(笑)。
---最終ジャッジも自分で?
浦田 もちろんディレクターさんには見せるんですが、「まんまでいいと思うよ」と言ってもらえることが多かったですね。
藤井美保(音楽ライター)
大学卒業後、音楽関係の出版社を経て、作詞、作曲、コーラスなどの仕事などを始める。ペンネーム真沙木唯として佐藤博さん、杏里さん、鈴木雅之さん、中山美穂さんなどの作品に参加。その後、音楽書籍の翻訳なども手がけるようになり、93年頃からはライターとしてのキャリアも。